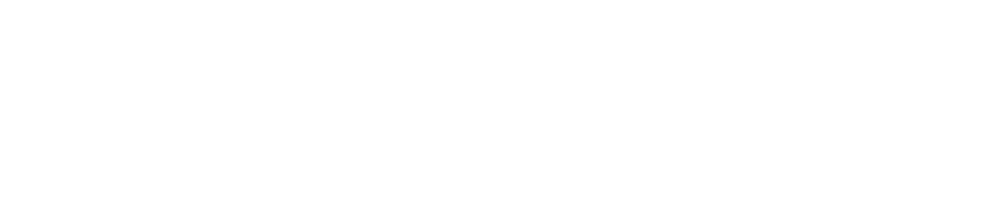タイプ・ウッドの提案について
大阪・関西万博に木材の活用を

大阪パビリオン建設に際しての国産木材の活用
2022年6月1日
2025年日本国際博覧会 大阪パビリオン建設に際しての国産木材の活用について
一般社団法人 大阪府木材連合会 会長 津田 潮
一般社団法人 大阪府木材連合会は、会員に丸太素材生産、木材製品加工生産、木材流通市場、木造住宅建設等業種別団体20団体を数える木材業に係る一般社団法人であり、大阪築城以来永い伝統と歴史のある大阪の木材界の連合会として活動を続け、極めて顕著な実績を有しています。
今後円滑な木造建築計画・設計・施工を推進するためには、生産者から消費者、木材資源を有効利用するための情報のプラットホームが不可欠であり、木造建築関係者が容易に情報交換を行うとともに、それら関係者の協業により中規模以上を含めた木造建築物の建築を促進するため、建築士(意匠、構造)、試験研究機関(大学、府県木材・住宅関係研究機関)、審査機関(近畿木造住宅協会)、木造関係資材・工法会社(木造構法・防耐火、不燃構法・JAS機械等級構造材・木製フローリング、木造用金物)、木材関係工場(ツーバイフォー・プレカット・NLT等)、木材供給団体(各府県木材連合会、森林組合等)ゼネコン・ビルダーをメンバーとする、「関西広域木造建築普及促進協議会(会長 五十田博京大生存圏研究所教授)」の事務局を司り、地元大阪を始め府県を越えて西日本の川上と川下を繋ぐパイプ役の
中心として国産材の土俵拡大に資するように努力を重ねて参りました。
大阪府においても、2022年5月に建築物における木材利用を一層促進させるために、大阪府木材利用基本方針 を改正し、府が行う建築物の整備の実施に当たっては、原則として木材を利用した方法を採用するとともに、市町村に対しても積極的な木材の利用を要請するほか、 林業及び木材産業の民間事業者が、建築用木材等の適切かつ安定的な供給 の確保に努めるよう働きかけるとともに、民間事業者が整備する建築物に対して、 木材の利用を積極的に働きかけていくものとされています。
さて、2025 年日本国際博覧会が目指すのは
☑ オール大阪の知恵とアイデアを結集し、「いのち」や「健康」の観点から未来社会の新たな価値を創造するとともに、大阪の活力、魅力を世界の人々に伝える。
☑ 世界の先頭に立ってSDGsの達成に貢献するため、〈SDGs先進都市〉の姿を明確にし、SDGs達成目標の2030年以降を見据えた取組を世界へ発信。
そして、大阪パビリオン建設に際してのキーポイントは
①サスティナブルな素材である木材の積極的な活用
②トータルコストの縮減と建築資材のリユース
③関係各府県木材連合会等との連携による、地元大阪を始め近畿・西日本からの木材・木質材料の確実な調達
の3点であると考えます。
私たち大阪府木材連合会は、大阪パビリオンの建設に際し、十二分に対応して限られた期間内に地元大阪材をはじめ、近畿・西日本の国産材の調達やNLT(マス・ティンバー)等、新しい建築木製品の紹介やサポートを行うとともに、大阪府や関係府県、木材関係団体、建築士等と連携して買い戻し方式等も含めた具体的なリュースに関する提案・情報発信をしていきます。
〔お問い合わせ〕 大阪府木材連合会 専務理事 三宅・事務局長 橋本 大阪市住之江区平林南1-1-8 Tel 06-6685-3101
2025大阪関西万博
2025年の日本国際博覧会に向けて木造パビリオンの提案

ショーン・ローラー 大阪府木材連合会副会長 カナダ林産業審議会日本代表
今村祐嗣 大阪府木材連合会特別顧問 京都大学名誉教授、建築研究協会常務理事
カール・ベンクス 大阪府木材連合会特別顧問 古民家建築デザイナー
畠山重篤 大阪府木材連合会特別顧問 NPO法人森は海の恋人理事長
ジョン・ギャスライト NPO法人ツリークライミングジャパン理事長 中部大学教授
川合秀一 大阪府木材連合会特別顧問 京都大学名誉教授、同大学生存圏研究所特任教授
大阪関西万博へ木造パビリオンを提案
会長 津田潮氏

また、木材の需要拡大のため強く推進しておりますのが、NLTです。昨年、準耐火構造材の大臣認定も取得いたしました。 府木連が入る大阪府木材会館にも使用しています。NLTは曲線を表現でき、デザイン性に優れています。断熱や調湿の機能も併せ持ち、室内空間をより快適なものといたします。 くぎによる強い接合力により、耐力面材としての利用価値が高いという特長がございます。NLTのメリットといたしまして、CLTと同等以上の高い強度、製造に伴う大規模な設備が不要、接着剤不使用によるVOC(揮発性有機化合物)の発生ゼロ、造形の自由度があります。 単価はCLTの3分の1程度ということで、使いやすい価格になっております。
公共建築物等木材利用促進法が10年前に施行されましたが、1000平方メートル以上の木造には耐火構造が要求され、それがネックとなり、意図したほど木造建築物は増えておりません。 耐火構造をクリアするために、鉄骨やコンクリート造と木造との混構造という方法もあります。木ばかりにこだわるのではなく、木と鉄の組み合わせなど、自由な発想で木の需要を開拓し、建物内部の木質化も進めていきたいと思っております。 いま取り組もうとしているのは、建物のフロントを形作るカーテン・ウォールのアルミ・サッシとガラスの木材の内貼りを加え、開放感や高級感のある室内を作ることであります。
マス・ティンバーは国際的なトレンド
ショーン・ローラー氏
19年の数字を見ますと欧州でCLTの市場は100万立方メートルに近くなりました。少し遅れましたが、北米に広がります。25年までにマス・ティンバーの市場は330万立方メートルまで成長すると予測されています。
初めは学校などの建物で先導的に使われていました。現在、住宅や高層ビルなど、幅広くマス・ティンバーの建物が出てきました。なぜかというと、木造建築の技術が発展してきたからです。
日本国内でもCLTやNLTが広がる可能性はあります。ツーバイフォー工法でマス・ティンバーを使えば工場生産による合理化や労働負担の軽減など、さまざまなメリットがあります。
われわれカナダ林産業審議会としては、日本ツーバイフォー建築協会と共同でNLTを推進したいと思っています。マス・ティンバーが高層ビル建築に使われるようになると、今までとは建築方法が変わってきます。
ハイブリッドといいますか、混構造を考えるべきと思います。

未来社会支える木材の利用に強い意識を
今村祐嗣氏
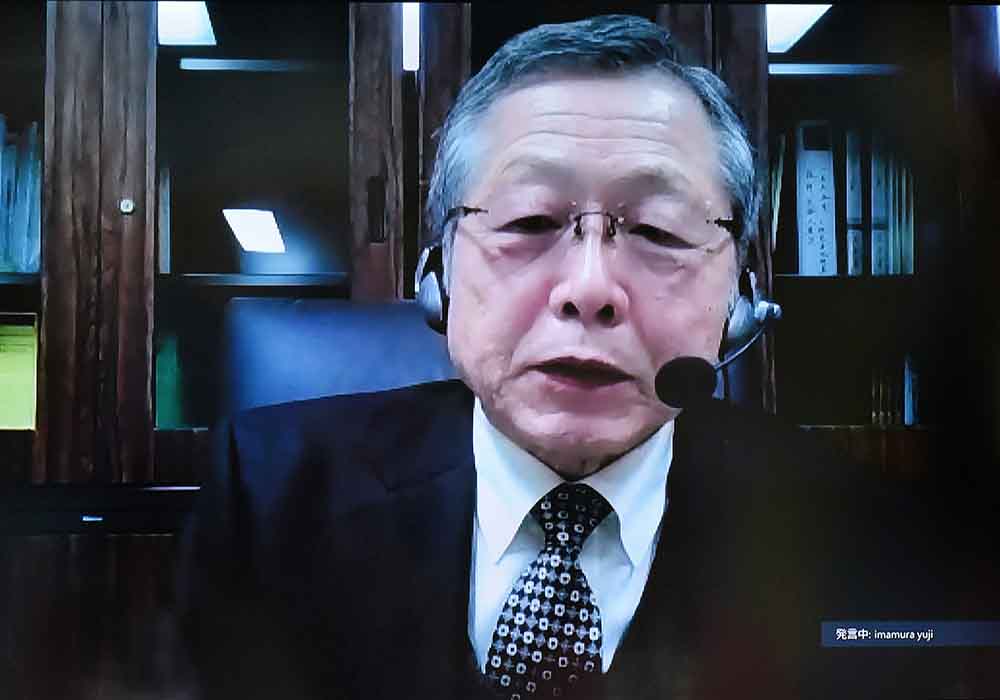
特に日本の場合、塗装をしない白木をそのまま使うことにこだわる、あるいは薬剤に対する考え方が外国とは違うということがあります。防腐処理した木材の1人当たりの使用量で比べますと、米国は日本の100倍以上あるわけですね。
長持ちさせるという面では今後、考えていかなければならないところがあるのではないか。日本人は往々にして木の優しさにこだわり、これまた、一般の方々の共感を得やすい当たりの良い
言葉ですが、一方で、ふつうの材料として捉え、扱い、これからの社会は木材が支えるのだという強い意識をもつことが大切だと思います。木材はいろいろな特質を持っています。
持続的な資源利用や炭素固定による温暖化防止効果はもちろん、軽くて強い性能、高い意匠性、等々をアピールしていただいて、大阪・関西万博のテーマ「いのち輝く未来社会のでデザイン」のなかに新しい木材利用のあり方を位置付けていただきたいと思っております。
日本の木造建築の技術を大事にしなければ
カール・ベンクス氏
送っても大工さんが行けないということで困っているんです。何がいいたいかというと、外国人は日本の伝統的な木造建築に興味があります。日本の木造建築は世界一ですよ。
せっかくの技術をもってるのに残念ながら、だんだん失われているんです。若い職人もいないんです。若い人は、この職業に就きたいけれど、なかなか生活できないんです。もっと木の仕事を認めなければと思います。
木の育て方も世界一ではないか。その技術もだんだん失われているんですよ。大阪・関西万博で日本の伝統的な技術を見せなければと思います。日本人は、あまり興味がないようですけど、外国から来る人は興味があるんですよ。
日本人は興味がないのではなくて、学校で教えないからですよね。若い設計しに聞いても、なかなか学校で教えてくれないと言います。残念だと思います。
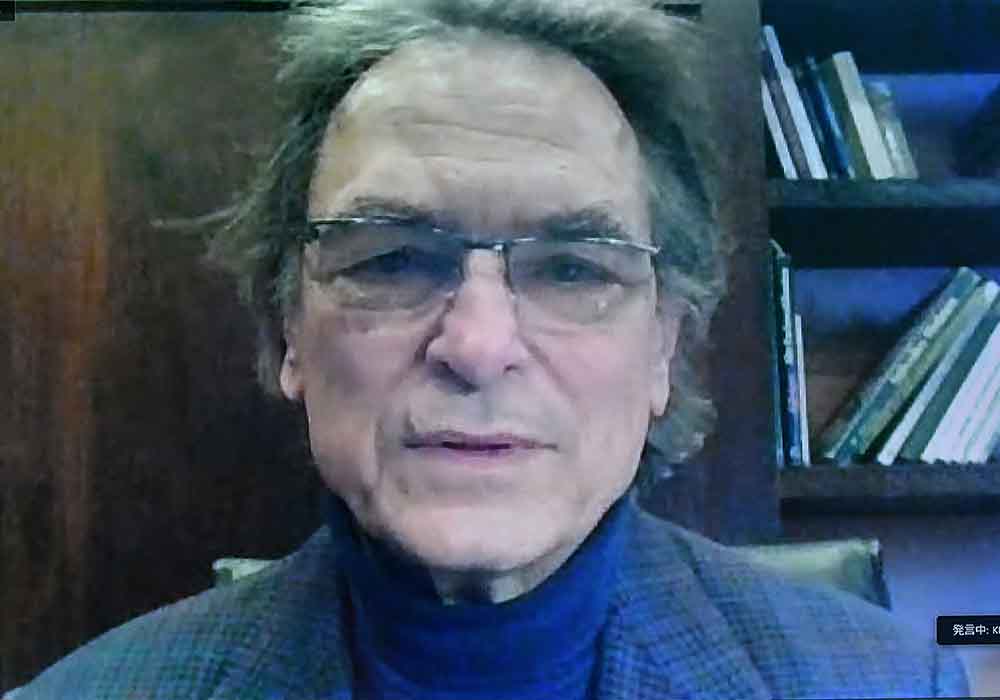
森林は海の生き物にとっても重要な存在
畠山重篤氏
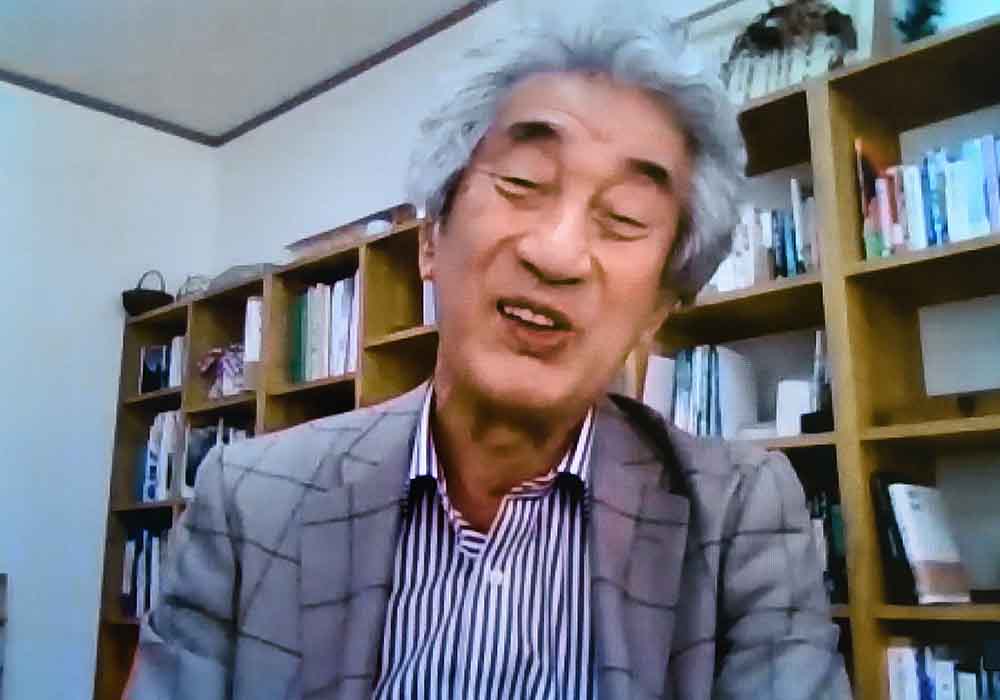
調査にきてくれた魚類学の先生が「安心してください。カキが食べきれないくらいプランクトンがいます。『森は海の恋人』の勝利です」とおっしゃったわけですね。
私たちは、いいカキを作るには森林が大事だと気が付きまして、「森は海の恋人」として海に注いでいる川の背景にある山で植林を30年、続けてきたんです。
森林の養分が川から海に流れてプランクトンが発生するという関係は、津波で壊れなかったんです。海の生き物にとって森林がいかに重要かを証明したと思っているわけです。
CO2(二酸化炭素)のことを考えるときに、陸上の森林だけではなくて、海の森林、植物プランクトンのことも考えなければいけないと思うんですよ。
森林の養分がないと、海の森林はCO2を固定化できないということですね。だから、森林は重要なんですよ。木材の活用に、そういう考えをプラスして、アピールすれば、発展していくのではないか。
日本の間伐の技術が米国の巨木を守った
ジョン・ギャスライト氏
研究所も立ち上げました。日本の林業に関する素晴らしい技術を海外に紹介したいという気持ちがありますね。昨年、米カリフォルニア州の巨木、ジャイアント・セコイアの森が大火事になりました。
実は土地を所有し、巨木を保護しています。たくさんのジャイアント・セコイアが燃えてしまって、がっかりしていたらジョンさんのところは、周りに木がないようにしていたから残っていたと、エキサイティングなニュースが入ってきました。
小さな山火事を全部、消してしまっていると、シャイアント・セコイアの周りにいろいろな木が生えてきて、大きな山火事になったとき、ジャイアント・セコイアに燃え移ってしまうんです。
日本には間伐の伝統があります。研究所のトレーナーたちを連れて、ジャイアント・セコイアを傷つけないように、周りに木を間伐する計画を進めていたんです。日本の技術を世界に広げていきたいと思います。
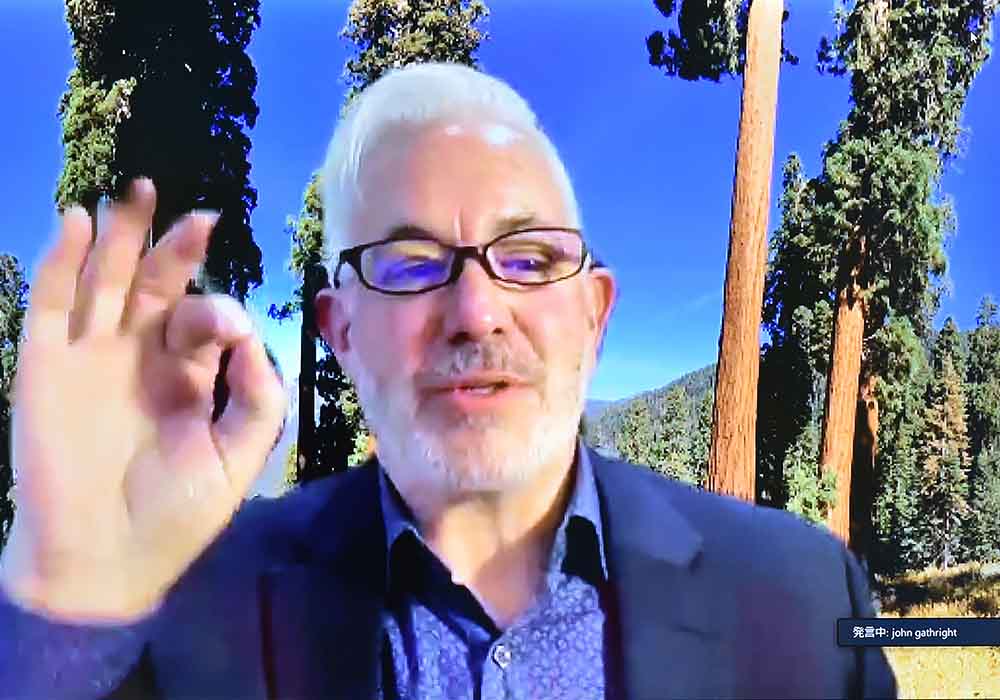
内装のスギ材、心身への効果を調査
川井秀一氏

今年度の林野庁の補助プログラムに例えば、オフィスビルや公共建築物のほか、スターバックスやローソンといった人々がよく使う場所に内装材としてスギ材を使っていこうということに補助金をいただいています。
現在は海遊館の近くにあるベジタブルレストランで、壁の4分の3くらいを「杉木ロスリット材」で改装しています。
府木蓮が普及を推進しているものですが、これまでにない贅沢なものです。改装した店舗が開店いたしまして、すでに営業に入っております。
そこで働く従業員の方に心拍数を測る生理実験や心理的なアンケートを取る実験をさせていただいたり、そこに来られるお客様にも内装の環境をどのように感じるか、木の香りはするのかといった調査をさせていただいております。
こういった試みを通じて、大阪を中心に木材の利用を推進し、国産材を利用すると同時に、それを維持する林業の技術も含めて、大阪・関西万博でアピールさせていただければと思います。